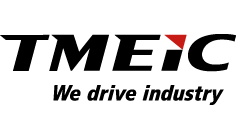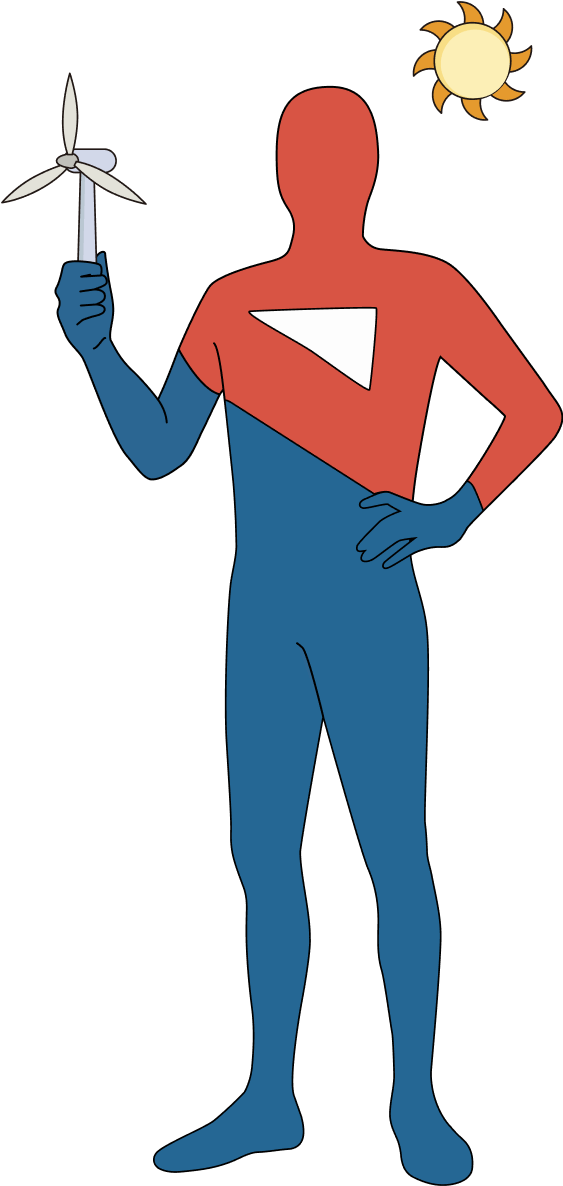

イメージ

産業・エネルギーシステム
第一事業部
エネルギーソリューション技術部
近藤 優駿

産業・エネルギーシステム
第一事業部
エネルギーソリューション技術部
木村 優杜
「再エネ+貯める」で、
エネルギーは新時代へ
2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、日本は2040年度までに総発電量に占める再生可能エネルギー(再エネ)の割合を40〜50%へと引き上げる方針を掲げている※1。中でも太陽光は、2023年度の9.8%から、2040年度には23〜29%へと大幅に割合が増え、主要な発電方法の一つになると見込まれている。
太陽光発電は、様々な発電方法の中でも設置コストが低いことがメリット。しかし天候や昼夜で発電量が大きく変動し、電力の安定供給が難しいのが課題だ。例えば1日の電力需要のピークは夕方※2であるのに対し、この時間帯は太陽光の発電量が減ってしまい、需要と供給のバランスがとれない。
自然現象を利用する再エネならではの、安定性に欠けるという課題。この解決策となるのが、発電した電力を「貯める」という方法だ。例えば、昼間に発電した電力を「蓄電池」に貯めておき、夜間に放電すれば、電力を各地へ届ける送配電網(系統)に昼夜を問わず一定の量を送り出せる。複数の蓄電池を備えた「蓄電所」と呼ばれる設備を系統上に増やすことで、再エネを含めた電力の需給バランスの調整や、系統の安定化につながることから、蓄電池や蓄電システムへのニーズが高まっている。
しかしここで問題なのが、大容量の蓄電池を設置するには一定の広いスペースが必要になることだ。今後、再エネの割合を目標値まで引き上げるには、狭い土地を活用した小規模な蓄電所を各地に増やすことも重要になる。土地によって面積や形状に様々な制約があるなかで、蓄電池の設置をどう進めていくかが課題となっていた。
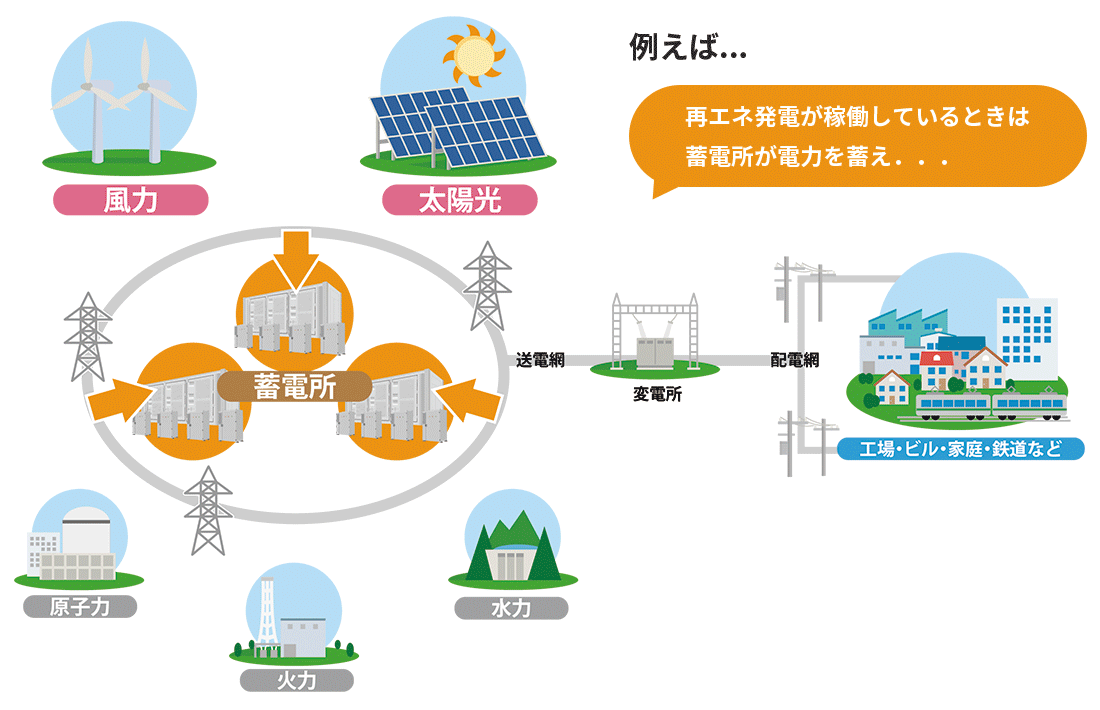
- ※1出典:資源エネルギー庁「エネルギー基本計画の概要」
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218001/20250218001-2.pdf#page=9 - ※2出典:出典:資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの長期安定的な大量導入と事業継続に向けて」
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/saisei_kano/pdf/061_02_00.pdf#page=48
「現場発」のソリューション
フレキシブル蓄電システム
蓄電池を設置するにあたってのスペースの問題。ここにTMEICが注目したのは、太陽光発電の現場で生じていた、ある変化がきっかけだった。TMEICはこれまで、メガソーラーと呼ばれる大規模太陽光発電所に併設される大型蓄電池のプロジェクトを各地で手掛けてきた。その過程で現場の担当者たちは、太陽光発電所の立地環境や規模が、年々多様化していることも目の当たりにしていた。狭い土地や傾斜地を利用した発電所では、蓄電池を設置したくてもスペースが足りずにあきらめる顧客もいた。「日本全体で再エネをもっと拡大していくためには、『場所を選ばず設置できる蓄電池』の実現が必要不可欠でした。当時、実際に現場で多くのTMEIC担当者がそのニーズを肌で感じていたことから部門を挙げて開発に乗り出しました」と技術営業を担う近藤は説明する。
開発を進める過程では、複数の顧客に入念なヒアリングを実施。その内容を踏まえて製品アイデアを顧客に提案し、そこで得た結果をフィードバックし、社内で検討を加え、ブラッシュアップした案を再び投げかける。これを繰り返すことで、発電所ごとに異なる事情やニーズに寄り添えるソリューションを探っていった。
こうして完成したのが、太陽光や風力発電所に併設でき、蓄電所としても活用可能な「フレキシブル蓄電システム」だ。最大の特色は、設置する場所に合わせて蓄電池の総容量や配置レイアウトを柔軟に選べること。このシステムはパワーコンディショナ(PCS)※3と小容量の蓄電池で構成され、PCSは最大3台まで1つのコンテナに収納可能。そこにつなぐ蓄電池は、合計で最大30台まで増やせる。つまり30パターンの組み合わせから、土地のスペースや形状に応じたカスタマイズができるのだ。
現場の声から生まれた、今までありそうでなかった柔軟性の高い蓄電システム。TMEICが培ってきた技術力と、顧客と積み重ねた何往復ものキャッチボールが合わさることで実を結んだ「現場発」のソリューションといえる。
- ※3パワーコンディショナ…電力の直流・交流を変換する装置。蓄電池に貯蔵された直流電力を系統に連系できるよう交流電力に変換したり、また逆に系統からの交流電力を蓄電池に貯蔵できるよう直流電力に変換を行う
「貯めて、使う」をシステムで最適制御
TMAuroraの監視画面
蓄電システムを長く安全に使う上で重要になるのが、蓄電池に過度な負担がかかる状態を防いで劣化を抑えることだ。従来の大型蓄電池なら、1台だけを監視すれば良かったが、「フレキシブル蓄電システム」は最大30台の蓄電池を連携させる。使用するなかで蓄電池ごとに差が出る劣化の度合いを把握しながら、全体を最適に制御する必要があるのだ。
そこでTMEICは、発電所や蓄電所の発電状況を監視・分析する「TMAurora(TMオーロラ)」を開発。TMEIC初となるクラウドを活用したシステムで、発電所や蓄電所の充放電状況を常時モニタリングし、最適制御する。蓄電池ごとのコンディションの把握や、想定する蓄電池の運用方法からの逸脱をお客さまへ通知する機能も備えている。
開発に携わった木村は、システムの仕様を決定するまでの難しさを明かす。「発電事業者によって異なる蓄電池の運用方法を考慮しつつ、電力会社が求める要件に応えられるようにシステムの仕様を工夫しました。太陽光や風力の発電所は、山間部など通信環境の良くない地域にも多くあります。そのためどのような電波環境でも安定してシステムが稼働するよう、通信装置も含めた動作確認を慎重に進めました」と振り返る。
「TMAurora」には、設備の運転状況データを遠隔で取得できる機能も備わる。従来は、落雷などで系統への送電が緊急停止したときは、TMEICのメンバーが現場に足を運んで原因や状況を確認するときもあったが、その手間が不要に。リモートでデータを取得・分析し、問題がなければ遠隔サポートの上、現場主任技術者にて運転を再開することができる。管理者の負担を大幅に減らすと同時に、迅速な復旧対応が可能になった。
ハードとソフトの合わせ技で
より良い環境を次世代に
蓄電池や蓄電所の導入を促進する取り組みは全国で進んでいる。今後は工場や商業施設、公共施設などで、災害時・停電時への備えも兼ねて蓄電所を設置するケースが増えると予想される。既存施設の限られたスペースでも「フレキシブル蓄電システム」なら設置しやすい。
「蓄電システムは比較的新しい分野で、今後も機能や使い方について様々な要望が寄せられるはずです。自分自身が電力インフラの課題の最前線に立って、お客さまの声を直接聞き取り、ニーズに沿った提案ができることに大きなやりがいを感じています。フレキシブル蓄電システムとTMAurora。このTMEIC独自のハードとソフトの組み合わせで課題を解決し、再エネの導入拡大を後押ししていきたいと思います」(近藤)
前職でプラント関連のシステムエンジニアリングに携わっていた木村はこう語る。「前職の現場では時に、産業の発展に伴い自然環境が傷つけられた時代の爪痕を目にすることがありました。業界を問わずあらゆる企業がカーボンニュートラルの実現に真摯に取り組んでいる今、私自身も、地球環境を少しでも良くする仕事に経験と知識を役立てたいと考えたことがTMEICを志望した理由の一つです。再エネの普及に貢献することは、次世代により良い環境を残すことにもつながる。そう信じられるからこそ、これからも迷いなく全力で仕事に臨んでいきます」(木村)
2040年、再エネが主要な発電方法となる社会へ――。現場のニーズを的確につかみ、技術力で応えるエンジニアたちが、日本が目指す未来を実現する一翼を担っている。